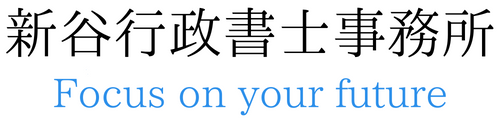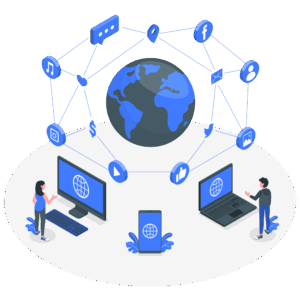民泊の消防設備は自分で設置できる?
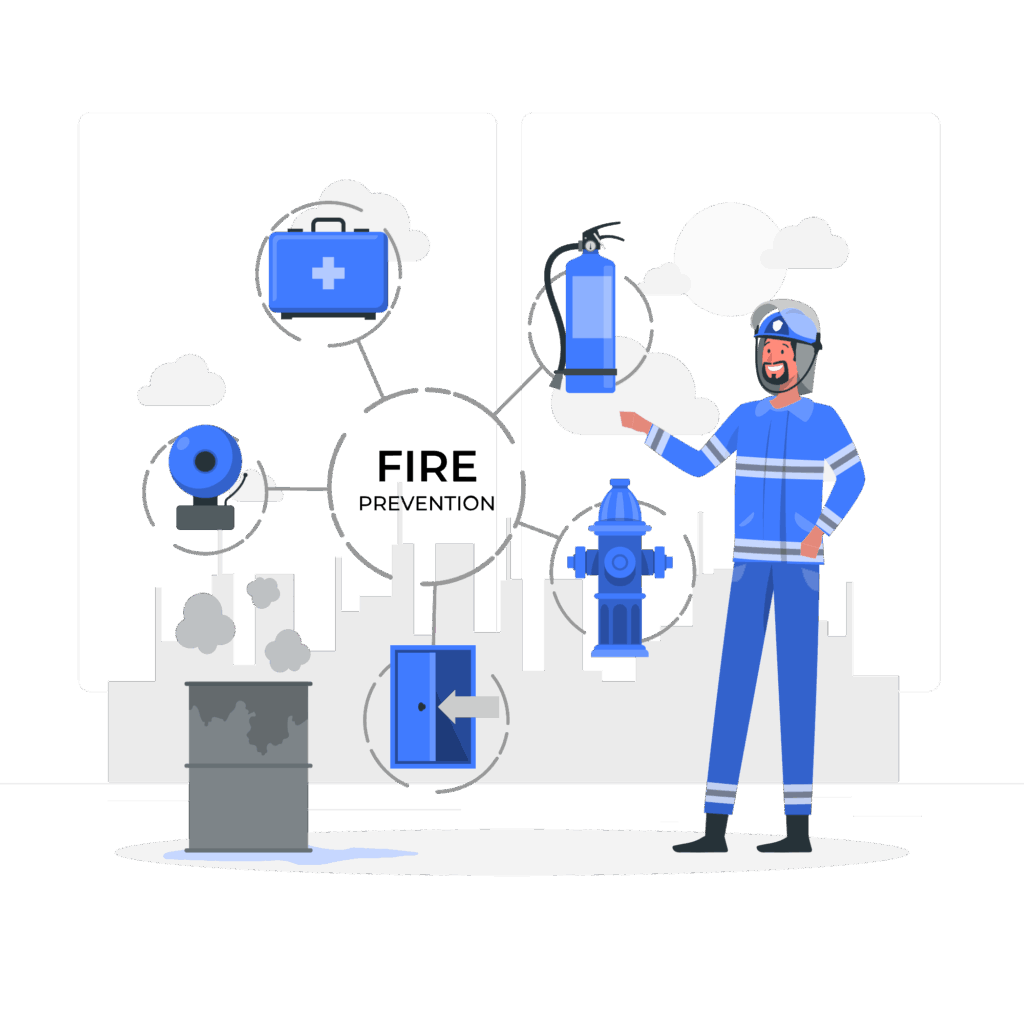
民泊を開業するまでには1ヶ月~3ヶ月くらいはかかるのが一般的と思います。結構やることが多くて大変ですよね。
また、手続きに費やす時間と同じくらい費用のことも考えていかなくてはいけません。許認可の申請など自分でできることを自ら行えば費用を抑えられるかもしれませが、消防設備の設置に関しては消防設備士の資格が必要となってきます。
必要な消防設備について
民泊に必要な消防設備に関しては、戸建てやマンションなどの建物の種類、床面積、階数など様々な要素から総合的に判断されます。特にマンションなどの共同住宅は民泊をする部屋のみではなくて建物全体で判断されることになります。実際に消防署に相談に行っても話の内容がよく分からなかったと思う人も多いので、基本的には消防設備会社に頼んだ方が良いでしょう。
・自火報
・誘導灯
・消火器
一般的には上記の設備が必要になってきます。共同住宅では状況によっては発報元を特定するための総合盤を設置するような大掛かりな工事が必要になるケースもあり、その場合だと工事費用は高額になってしまい結果としてその物件での民泊運営をあきらめる人もいます。また、逆に今設置してある設備を利用でき、携帯用照明(懐中電灯や非常灯など)のみで良かったというケースもあります。
※非常用照明は建築基準法に基づくものなので、役所などの建築基準法の窓口で相談してください
特小自火報について

絶対に必要な消防設備として自火報(自動火災報知設備)があります。この報知機を天井に設置するのですが、配線工事が必要なので消防設備士の資格を持った人でないと行うことができません。。
ただし、一定の条件下では特小(特定小規模施設用自動火災報知設備)という自火報を設置することができます。300㎡以下の建物、もしくは300~500㎡以下の共同住宅で住居と宿泊施設のみの建物、などの要件で設置が可能となります。
この特小はそれぞれの機器が電波で連動する仕組みとなっており、天井にネジで固定するだけで配線工事が不要のため消防設備士の資格がなくても設置できます。能美防災とパナソニック製がありますがAmazonでも購入が可能です。親機と子機、熱・煙で感知するタイプがあります。
注意
住宅用の報知器と形が似ていますが、住宅用のものは民泊には使えませんので注意してください。「特定小規模施設用自動火災報知設備」と書いてあることを確認してください
誘導灯の免除特例

誘導灯も基本的には必要になり、出入口や通路、階段などに設置しなければいけません。
この誘導灯について免除特例があります。免除特例を適用するには戸建てと共同住宅で要件が違いますが、各部屋から廊下に出て避難経路が分かりやすいのが前提で、開口部、非常用照明や携帯用照明器具の設置、間取りなどいくつか要件があります。共同住宅では難しいかもしれませんが、一般的な戸建ては免除特例が適用されるケースも多いです。
注意
自治体の消防条例や消防署の判断に依るところがありますので、詳しくは管轄の消防署へご相談ください
消火器は自分で買える
小さめの戸建ての場合は床面積によって消火器が不要で、共同住宅の場合でもすでに廊下に設置してあるので新たに設置する必要はないケースも多くあります。しかし、設置義務はなくても消防署からお願いされて設置してくださいと言われます。個人的にも消火器が不要の場合でも購入して民泊施設内に置いておくことをお勧めします。万が一の場合に備えれますし、近隣の住民も安心することと思います。消火器はホームセンターやネットでも簡単に購入できます。
その他
キッチンのコンロの形式にはガスとIHがあります。ガスコンロには自動的に火が消える機能がありますが、火災防止を考えるとIHにした方がより安全かもしれません。しかし、IHの場合は電気を使用するので、調理と同時に他の家電を作動することによってブレーカーが落ちる可能性もあります。どちらにするかは総合的に判断してみてください。
自分で消防設備を設置する
✅ 自火報が特小でOK
✅ 誘導灯の免除特例が適用された
上記の2つともを満たす場合であれば、消防設備の設置を業者に依頼せずに運営者自ら行うことが可能です。ネットで必要な数の特小報知機、非常灯(ホテルによくある壁掛けの懐中電灯みたいで外すと自動的に点灯するやつ)、消火器を購入し避難経路図を自分で作成するだけでよくなり、大幅に消防設備へのコストを削減できます。
◎私が開業に関わった民泊施設を一例として紹介します。
【物件情報】
・木造2階建ての戸建て
・約90㎡
・2LDK
【必要な消防設備】
・特小の自火報8個
・非常灯3つ
・消火器2本
※誘導灯は免除特例が適用済
消防設備の費用約12万円
最初に運営者が消防署に相談した時には誘導灯も必要で、もしかしたら非常用照明も必要かもと言われたみたいです。その条件で消防業者に見積を取ると約40万円だったそうです。地方都市ではあるかもしれませんが、民泊の数が少なくてそこまで民泊の消防設備に詳しくない職員の方もいます。結果的に私が代わりに再度相談に行って、誘導灯の免除特例は適用できるはずと説明することで適用されました。コスト的にはかなり削減できました。
自分で設置する際の注意点
業者に依頼せずに消防設備を設置することは可能ですが、消防署に提出する書類の作成と定期の点検・報告を自分でしなければいけませんので注意が必要です。
書類作成
設置前に提出する書類(工事計画書、概要表、図面、付近見取図、特例申請書など)と設置後に提出する書類(設置届、使用開始届、配置図、仕様書、試験結果、適合通知書交付申請書など)
書類作成については記入例もありますし、不明な点は消防署から教えてくれます。ただ、事前相談から始まり、設置前の書類提出、設置後の書類提出、適合通知書の受取など、何度も消防署に足を運ぶ必要はあります。
定期の点検・報告
宿泊施設の消防設備は6ヶ月ごとの定期点検(目視による外形検査)、1年に1回の総合点検(実際に自火報を作動させる)と報告書の提出
点検票の記入例は消防庁や自治体のホームページにあり、自治体によってはオンラインで提出できるようになってます。また、特小には自動試験機能が付いておりボタンを押すだけで容易に作動させることができます。業者が持っている棒の先にカップ状のものがついてある検査装置は必要ありません。
まとめ
消防設備を自分で設置することが可能な場合はコストを抑えれますが、書類作成は面倒で点検時期も覚えておかなくてはいけません。コストはかかりますが消防業者に依頼することで負担を下げれますし、何より宿泊者の安全面を考えると業者に依頼した方が安心かもしれません。コストと負担とどちらを優先するかいろいろ検討してみてください。