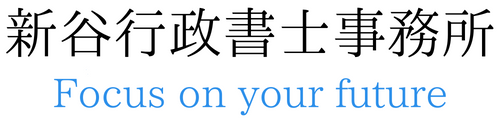【旅館業と住宅宿泊事業のどちらで運営するか?】それぞれのメリットを解説
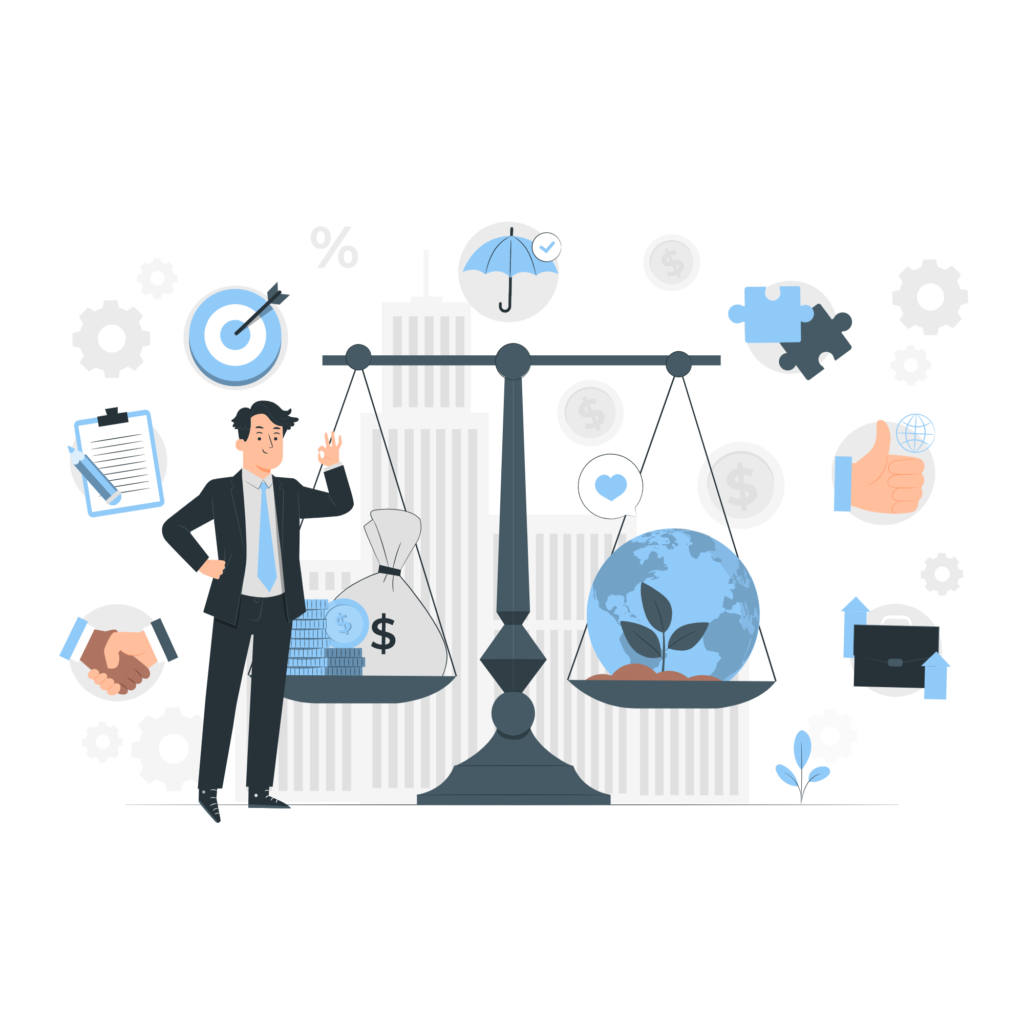
旅館業と住宅宿泊事業の比較
| 旅館業 | 住宅宿泊事業 | |
|---|---|---|
| 営業日数 | 制限なし(365日営業可能) | 年間180日以内 (条例で実施期間の制限が可能) |
| 住居専用地域での営業 | 不可 | 可能 (条例により制限されている場合あり) |
| 建築基準法上の建物用途 | ホテル又は旅館 | 住宅/共同住宅/寄宿舎/長屋 |
| 最低床面積 | 33㎡以上(ただし、宿泊者数10人未満の場合は1名あたり3.3㎡) | 1名あたり3.3㎡以上 |
| 消防用設備等の設置 | 自動火災報知設備、非常用照明、避難誘導灯など | 家主滞在型で宿泊者の寝室が50㎡以下なら、住宅用火災報知器のみで可。家主不在型なら旅館業と同様の基準 |
| 管理業者への委託義務 | なし | あり (家主不在型) |
| 営業日数等の定期報告の必要性 | 不要 | あり(2か月ごと) |
| 申請手数料 | 必要(自治体によって異なる) | 不要 |
旅館業のメリット
営業日数に制限がない
旅館業法に基づく営業許可を取得する最大のメリットは営業日数に制限がないことです。これにより365日営業できて売上げを増やしていくことが可能で、営業日数を気にしなくて閑散期は単価を下げて稼働を上げていくような営業戦略もとりやすいです。住宅宿泊事業の場合は限られた日数の中で単価と稼働を考えながら料金設定をしていく必要がありますが、それに比べると旅館業の方が料金設定はシンプルだと言えます。
OTAへの掲載
現在、宿泊客のほとんどがOTA(オンライン上の旅行代理店)を通じて宿泊予約をしてきます。OTAには国内OTA(楽天トラベルやじゃらんなど)と海外OTA(AirbnbやBooking.comなど)がありますが、住宅宿泊事業の届出施設ではじゃらんなどの一部のOTAでは掲載不可となっており、旅館業法に基づく営業許可を取得することで販売チャネルが増え、施設の集客力を高めることができます。
管理業者への委託義務がない
旅館業の営業許可を取得した場合、住宅宿泊事業の様に管理業者(運営代行業者)への委託義務はないのですべての業務を事業者自身で行うことができます。清掃業務のみなど一部の業務を専門業者へ委託したり、家族や友人知人などに個人的に頼むなど柔軟に運営体制を構築することができます。
融資や補助金
融資を受ける際、借入元などによっては住宅宿泊事業の届出よりも旅館業の営業許可を取得した方が有利になることもあります。また、民泊に活用できる補助金の中には旅館業の取得が要件となっているものもあります。
ポイント
建築基準法の建物用途がホテル又は旅館以外で、使用する床面積が200㎡を超える場合は用途変更の確認申請が必要です。また、旅館業を取得できる用途地域が決まっており、申請するにあたり駆け付けや玄関帳場についてなどの要件が厳しく求められますので事前にしっかりと運営体制を整えておくことが必要です。
住宅宿泊事業のメリット
住居専用地域でも開業できる
住宅宿泊事業法の最大のメリットは、旅館やホテルの営業では認められていない住居専用地域での営業が可能な点です。自治体によっては条例により制限を受けることもありますが、これにより運営可能なエリアが広がりますので、検討する物件の選択肢が増えることになります。
空き家の有効活用
所有している空き家がある場合、そのままだと固定資産税などの税金や修繕費用などの管理費用のコストがかかり、その上誰も使用してない空き家は老朽化が進みやすく、周辺にも悪影響を及ぼすことも考えられます。しかし、民泊施設として活用することで収益を得ることができる可能性があります。
申請の簡易さ
民泊ポータルサイトを利用することでインターネット上で届出を行うことが可能です。実際には保健所や消防との協議が必要なのですべて完結するわけではありませんが、旅館業許可に比べると提出書類も少なく申請手続きは若干簡易的だと言えます。また、保健所職員による現地調査がないので申請から開業までは旅館業よりも一般的には早くなります。
運営のしやすさ
住宅宿泊事業の届出によって民泊を運営する場合、すべての業務を管理業者へ委託する必要がありますが、管理業者から事業者(運営者)へ再委託という形をとることで一部の業務については事業者自身で行えます。駆付けやチェックイン方法などの要件は旅館業よりも緩和されている自治体が多いですので、管理業者への委託費を抑えながら運営していくことも可能です。
ポイント
管理業者へ登録するための要件として以前は宅建等の不動産関連の資格か実務経験が必要でしたが、現在は管理者講習を受講すれば誰でも管理業者の登録が可能となっています。つまり自分自身で管理業者の登録をしてしまえば自主運営が可能になります。一般的に管理業者へ業務を丸投げすると売上の20~30%が委託費としてかかりますので、事業者自身が管理業者となることで運営コストを大きく削減できます。
まとめ
一般的に民泊を始めるには旅館業の営業許可もしくは住宅宿泊事業の届出が必要で、地域によっては特区民泊の認定という方法もあります。それぞれに違いやメリットがありますので物件の立地等の条件や運営方針なども考慮し、運営する自治体の条例を調べた上で民泊運営の参考にしていただければと思います。